「過去に嫌な出来事があり、その当事者を許せない」「長年恨み続けていて、一度間接的に謝罪を受けたこともあるが、それでも怒りが治らない」という方の話を聞きました。
状況によって対応の仕方は異なるので、幾つか備忘録として書き留めておきたいと思います。
怒りの目的
恨み」は「怒り」を解消できずにそのまま放置しておいた結果とみて、ここでは「怒り」にフォーカスを当てて考えてみます。
まず、目的論で見ると怒りにも目的があるはずです。
例えば、次のような目的です。
- 相手を支配したい
- 主導権を握りたい
- 自分の権利を守りたい
- 正義感を発揮したい
もしこのような目的のために怒りという感情を用いているのであれば、この目的を果たす他の方法があれば怒る必要がない、ということになります。
もし「怒りの感情を手放したい」と考えている方は、「自分は何のために怒っているんだろう」という観点を持つことから始めてみましょう。
一次感情と二次感情
 感情には「一次感情」と「二次感情」があり、「怒り」は二次感情に分類されます。
感情には「一次感情」と「二次感情」があり、「怒り」は二次感情に分類されます。
不安、寂しさ、落胆、悔しさ、心配などの「一次感情」が満たされない時に、怒りという「二次感情」を使って対応しようとすることがあります。
自分の感情の構造を客観的に見ることができるようになれば、まず「一次感情」を相手に伝えることによって、お互いの気持ちを理解しあえるチャンスが生まれます。
例)
私:「こうして欲しかったのに、そうならなかったので、私はとても寂しい」
相手:「あぁ、そんな風に考えてたのか。ごめん、気が付かなかった。次はそうしてみる」
こうなれば、怒りに発展する前に解決します。
むしろ、今まで以上に良好な関係を作れるかもしれません。
信念・価値観
 怒りの根底には「こうするべきだ」「こうしなければならない」といった本人の信念や価値観があります。
怒りの根底には「こうするべきだ」「こうしなければならない」といった本人の信念や価値観があります。
これに合わないことをされると一次感情の後に怒りが発生します。
例えば、理不尽なことをされて憤慨したとします。
「相手に非があるので、怒って当然」と私が思っていても、それをした当事者の根底にはその方の信念や価値観があって、「何故怒るのか理解できない」と感じているかもしれません。
つまり「私は正しい」「相手が間違っている」という思考を持っている限り、怒りから逃れることは難しく、相手から見れば、私も怒りの対象になってしまいます。
信念・価値観が人によって異なるのは当然の話で、それが問題ではなく、自分の考え通りに相手を動かそうとするところに問題があります。
誰が正しいか間違っているかではなく、「私はこう思う」「あなたの考えは?」と、お互いの意見を尊重して受け止め、一緒にできることがあるのか、協力関係を持つメリットがあるのか、を判断すれば考え方の違いでぶつかることはないでしょう。
信念・価値観とその人の人間性や人格は別なので、そこははっきりと分けて考えることが大切です。
その上で、感情的にならずに自分の考えや思いを正しく伝えることと、相手の意見もしっかりと受け止めて、共有ゾーンを見つけるコミュニケーションがとれるようになれば、怒りとは無縁の理想的なコミュニケーションに繋がります。










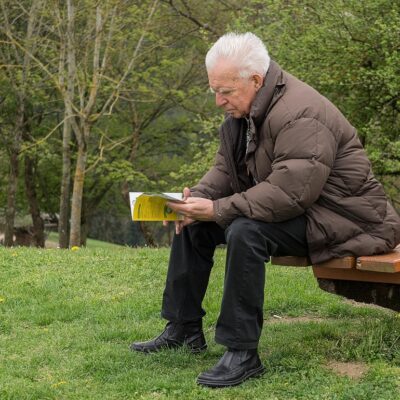




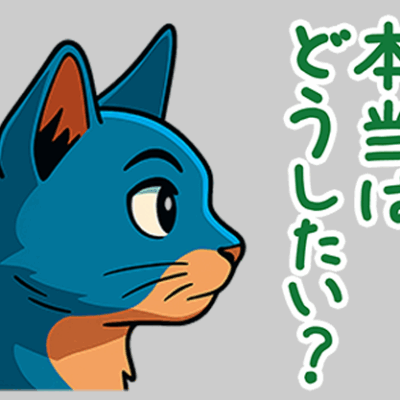









この記事へのコメントはありません。