心の時代
「21世紀は心の時代」と多くの人が語って来ました。
私が理解した内容を掻い摘んで言うと…
「20世紀は幾つかの戦争を教訓に、民主主義に舵を切り経済最優先で国(日本)を復興させてきた。
しかし、物の豊かさだけでは本当の幸せを得られないのが人間であり、これからは心の豊かさが重要視される時代になる」
概ねこのような意見が多かったと記憶しています。
現状はどうでしょうか?
自殺・他殺、いじめ・虐待、家庭崩壊、格差社会、環境破壊、競争社会…。
まだまだ心が平安に過ごせる世の中にはほど遠い気がします。
心の病
 心の病とはどういう状態を指すのでしょうか?
心の病とはどういう状態を指すのでしょうか?
精神疾患の診断基準としては、アメリカ精神医学会が作成したDSMや世界保健機関によってつくられたICD(国際疾病分類)があり、日本の医療関係者にも用いられています。
DSM-5の日本語訳を見ると、カテゴリーだけでも22項目に分類され、さらに各カテゴリーの中に細かい分類がなされ、精神疾患の膨大な量に圧倒されます。
これだけ研究されている分野であっても、原因不明の精神疾患が多いのは何故でしょうか?
脳の損傷など、明らかに根拠の有る症状は分かりますが、身体には問題の無い心の病の場合、状態を明確に伝えることが困難なため、「それは病気なのか甘えなのか」という混乱が学校や職場で発生する事例を耳にすることがあります。
医学的見地ではなくコーチングの観点から見ると、精神疾患を持つ方々に共通する特徴として、次の2点が挙げられます。
心の病に共通する特徴
 1. 物事を客観的に見ることができない
1. 物事を客観的に見ることができない
例えば「統合失調症」の症状に「妄想」があります。
「テレビで自分のことが話題になっている」「ずっと監視されている」など、実際にはないことを強く確信したり、「自分は天皇家の子孫である」などと思い込む「妄想」は、物事を客観的に見られない代表例です。
摂食障害で、平均値より遥かに少ない体重であっても「まだまだ太っているから体重を落とさなければならない」と思い込んでいる人も、物事を客観的に見られない状況に陥っています。
2. 目的と行動が一致しない
強迫性障害という病気があります。
手を石鹸で何度も繰り返し洗ったり、長時間シャワーで体を洗い続けたりします。
本当はそうしたくなくても、やめることができず自分の行動をコントロールすることが困難です。
鬱病を患ってしまうと、著しく気分が落ち込み、集中力がなくなったり、イライラしたり、ボーっとしたりして今まで出来ていた事が出来なくなります。
会社に行こうと思っても身体が動かないなど、自分の意思や目的と行動が相反するようになります。
心の病の根源
 ある臨床心理学の文献によると、心の病の背景にあるのは「不安」と説いています。
ある臨床心理学の文献によると、心の病の背景にあるのは「不安」と説いています。
人間は本来「安心・安全」を求めているため、不安になるとこれを解消するための行動を起こします。
しかし、不安が先立つと客観的に物事を見られなくなったり、目的と行動が一致しなくなるため、あまり良い結果を生みません。
また、不安が大きくなると「怒り」を引き起こします。
抱えきれない「怒り」は誰かにぶつけたくなります。
怒りを爆発させると、物を壊したり誰かを攻撃したりしますが、結果的に自己嫌悪に陥るなど反って不安が大きくなります。
また、怒りを外に出せない人は自傷行為に向かいます。
このように不安は、心の病の種となり、身体の病のリスクにもなります。
身近な例でご説明します。
「子供の帰りが遅い」=「不安(何かあったのでは…)」
→「遅く帰宅」=「怒り(こんな時間まで何してた!)」
このような種類の不安や怒りは、どなたでも経験があるのではないでしょうか?
さらに、正体の分からない不安、又は自分ではどうすることもできない不安は「恐怖」になり、「恐怖」が大きくなると「絶望」になります。
上記の例のように「子供が心配」から発生するような「不安」は、決して悪いものではありません。
しかし「不安」の種類によっては「怒り」となり、破壊衝動を持ったり、「恐怖」や「絶望」に発展すると心が病んでしまい、いわゆる精神疾患になる危険があります。
2種類の不安
 コーチングセッションでも、クライアントの様々な課題や悩みを深掘りしてみると、根底には不安があるというケースが大変多いです。
コーチングセッションでも、クライアントの様々な課題や悩みを深掘りしてみると、根底には不安があるというケースが大変多いです。
心の病の根底に不安があるとすれば、この不安を解消することで心の病を少しでも減らせるのではないでしょうか?
勿論コーチングは医療行為に代わることはできませんが、予防的な効果を発揮することはできるかもしれません。
私は、不安を2種類に分けて考えています。
一つ目は、自分の良心や信念に反するような方向に進みそうな時、「これで良いのかな?」などのシグナルを送ってくる不安。
この種類の不安は、上手に付き合えば私を良い方向に導いてくれる役割を果たしてくれます。
二つ目は、「何か悪いことが起こるんじゃないか」という根拠のない不安。
この種類の不安は、根拠がないため「思い込み」ということになります。
不安の対処法
 不安に対するコーチングセッションで良く行う事例を紹介します。
不安に対するコーチングセッションで良く行う事例を紹介します。
◇ 一つ目の不安の場合
不安にも「肯定的な意図がある」と考えます。
ですから、不安を排除しようとせずに「その不安は私に何を訴えているのだろう?」と不安を受け止め、不安が発しているシグナルに意識を向けます。
不安の肯定的意図に気がつけば、不安は安心に変わっていきます。
◇ 二つ目の不安の場合
客観的事実を確認していき、「思い込みだった」「思い違いだった」に気がつけば解決です。
しかし「何か悪いことが起こるんじゃないか」という思考癖のある人は、事実を認めることも難しい場合があります。
自尊感情
 二つ目の不安を抱えている人には、自己肯定感の低さや自尊感情に乏しいという特徴が挙げられます。
二つ目の不安を抱えている人には、自己肯定感の低さや自尊感情に乏しいという特徴が挙げられます。
両者を簡単に説明すると、自己肯定感は「自分の良さを肯定的に認める感情」、自尊感情は「評価に関わらず自分を価値ある存在として捉えている感情」です。
これらは、生まれ育った環境や人間関係などで形成されているため、簡単に変えられないかもしれません。
しかし、コーチとして出来ることは沢山あります。
自己肯定感や自尊感情が低いのは「勇気が挫かれている」、と見なすのがコーチの観点です。
勇気が挫かれていると、「どうせ私なんか」とか「やっても無駄」などの思考になりがちです。
そこでコーチが行うのは「勇気づけ」です。
勇気づけの中身は、主にコーチングのスキルにある「傾聴」「共感」「承認」に該当します。
「勇気づけ」を行うことで、「やってみようかな」や「これなら出来そう」など、自己認識に変化が生じます。
傾聴
https://adpa.site/coaching/active-listening/active-listening/
共感
https://adpa.site/coaching/empathy/empathy/
承認
https://adpa.site/coaching/acknowledgement/acknowledgment/
自己効力感
 さらに、自己肯定感を高める前段階として、「自己効力感」を高めるアクションを促します。
さらに、自己肯定感を高める前段階として、「自己効力感」を高めるアクションを促します。
自己効力感とは、「自分が行動すれば変化を起こすことができる」と思える気持ちです。
例えば、前回のテストが60点だった生徒が、頑張って勉強した結果、次のテストで70点を取った場合。
Aさん:10点上がって嬉しい。次はもっと頑張ろう。
Bさん:あんなに頑張ったのに10点しか上がらなかった。
Aさんは自己効力感が高い、Bさんは自己効力感が低い、ということになります。
コーチは不安を抱えているクライアントに、安心できる状態を聴き、そこに少しでも近づける方法を探し、簡単に出来ることから実践し、一つひとつ達成感を味わってもらいます。
こうすることで、自己効力感を高めていくことができます。
自己効力感が養われてくれば、自己肯定感も次第に高まって来ます。
最終的に、「自分を承認してもらった」、「自分の行動を誰かに受け止めてもらえた」「誰かの役に立った」という経験が「自尊感情」の向上に繋がると考えます。
まとめ
 「心の病」の背景には不安があります。
「心の病」の背景には不安があります。
不安には自分を正しい方向に導いてくれるものもありますが、根拠のない不安を抱えてしまう人は「自己肯定感」や「自尊感情」の低さが影響していると考えられます。
コーチは「自己肯定感」や「自尊感情」の低さは「勇気が挫かれている」状態と見るので、「勇気づけ」という関わりを持ちます。
また、簡単に実現できる小さな目標を積み重ねながら「自己効力感」を養い、「自己肯定感」を高めていきます。
自分を承認してもらう経験で「自尊感情」も向上していきます。
これらの働きかけで不安が解消すれば、「心の病」の軽減に繋がるかもしれません。









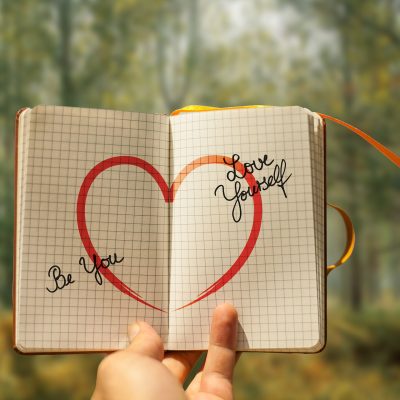
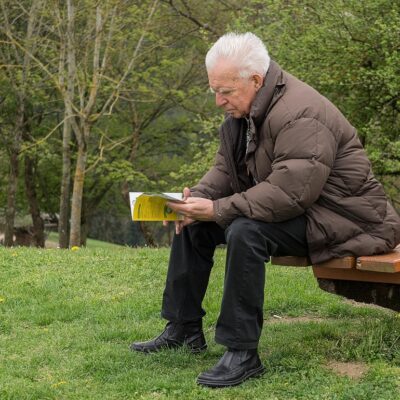




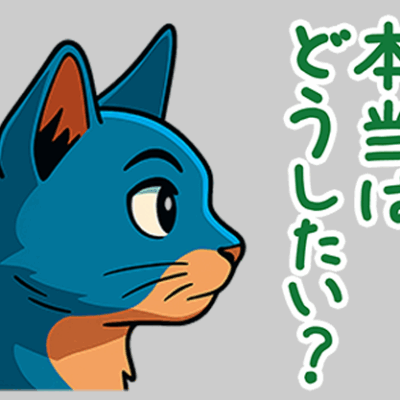










この記事へのコメントはありません。