東京都知事選
今回の東京都知事選(2024年東京都知事選挙)を皆様はどうご覧になったでしょうか?
都民ではないためあまり大きな関心事ではなかった、という方もおられると思いますが、私は大変興味深く観察していました。
コーチである私は、政治的な発言は控えています。
ここでは、コミュニケーションに関すること、そしてそれが私たち人生に与える影響についてお話ししたいと思います。
大学の講義に取り上げられる議会中継
 今回、今までにないムーブメントを感じたのが元安芸高田市長の石丸伸二氏(以下石丸氏)です。
今回、今までにないムーブメントを感じたのが元安芸高田市長の石丸伸二氏(以下石丸氏)です。
私は、彼が安芸高田市長として、ネットで話題になり始めた頃から興味深くウオッチしていました。
何故興味深いかというと、市長と市議会との対立がまるで正義と悪との戦いを描いているエンターテインメントのように映って見えるからです(どちらが正義・悪という意味ではありません)。
そして自治体のYouTubeチャンネルとしては、登録者数が全国で最も多く、当然市民以外の多くの視聴者も関心を持つコンテンツであるということです。
昨年、兵庫県の関西学院大学では安芸高田市議会をテーマにした講義が行われました。
生徒の感想の中には「絶望した」という声もありました。
恐らく市長が良い提案を出しても、理不尽な理由で否決されるという状況を見ての感想だと思います。
そのような石丸氏が今回の都知事選に立候補し、得票数2位という結果に終わりました。
知名度も高くない、告示当初はマスメディアも取り上げない、組織票も持たない中でのこの結果は驚異的です。
特に、無党派層と年代別で30代以下の得票数が1位だったという内容は、注目すべき社会現象です。
テレビ中継で何が起こったのか
 さて、コミュニケーションに関する本題に入ります。
さて、コミュニケーションに関する本題に入ります。
開票後のテレビ中継で、候補者にインタビューをする報道番組をいくつか観ました。
当然2位にいる石丸氏にもインタビューが集中します。
その時のやりとりが、どのテレビ局もあまりにもお粗末で、まるで噛み合っていない、コミュニケーションエラー頻発だったので、ある意味勉強になりました。
何故噛み合わないのか、私なりの理由を以下に挙げます。
◇ 目的が違う
テレビ局は限られた尺の中で、ある程度のシナリオを持って、想定通りの答えをもらうため、無難で曖昧な質問をします。
番組的に持っていきたい方向が見て取れます。
しかし、石丸氏は曖昧な言葉に対しては、受け流したり適当に答えることはしません。
恐らく、正しいことを正しく伝えることがメディアの仕事だと考えているため、番組の方向性に迎合しません。
論ずべきことや正しい言葉に拘る石丸氏にとっては、的外れな質問、間違った認識、曖昧な表現に対して、苦笑するしかなく、間違いを正すしかないという反応で、荒れるシーンもありました。
◇ 視点・視座が違う
テレビ局は、候補者個人の感想や気持ちを聞きます。時に感情を煽るような聞き方もします。
例えば、2位で嬉しかったのか?手応えはあったのか?敗因は何か?などです。
しかし石丸氏は、都民にとってどうなのか、延いては日本にとってどうなのかという視点や視座に立っているため「愚問だ」と苦言を呈しています。
◇ 意識の次元が違う
テレビ局の司会者やコメンテーターの質問内容は、候補者が今まで訴えてきた内容を調べれば分かる事ばかりです。つまり取材不足・勉強不足です。
これ自体が報道番組として失格です。
それに加えて、石丸氏の問題意識や政策に対する本質や本気度を理解できず、自分の考えが及ぶ範囲に引き摺り込もうとする見苦しい対応もありました。
つまり、本気で東京を動かす、日本を変えると思っている石丸氏と、そんな事は全く意識にない番組担当者とはどうしても噛み合わない、という構図に見えます。
コミュニケーションを成立させるためには
 コミュニケーションの観点に絞ってポイントをまとめます。
コミュニケーションの観点に絞ってポイントをまとめます。
◇ テレビ局:
- 相手の考えを理解した上で質問すべき
- さらに、短い時間枠で本質を引き出すためには、ピンポイントの質問を事前に準備すべき
- プロであれば、石丸氏のような知的エリートの言葉を理解できるリテラシーを持つべき
一方で、石丸氏が100%正しいとは言えません。
仮に主張している事が正論だとしても、コミュニケーションの取り方としては、課題もあります。
◇ 石丸氏:
- 挑発的な態度で敵を作るのは避けるべき(議会やメディア対応で、戦略的にそうしている可能性もあるが…)
- 相手の意見は否定しても、人格否定と誤解されるような表現は避けるべき
- 立場上必要な場面で相手を論破しても、別の場所で相手の立場や気持ちを受け止め理解する機会を持つべき(根回しではなく相手を理解するために)
正しい言葉の世界で生き、人生に意味を感じる
 最後に、今回の都知事選を通して、コーチとして学んだことを二つご紹介します。
最後に、今回の都知事選を通して、コーチとして学んだことを二つご紹介します。
人生に意味を感じているかどうかは、私が生きていく上でとても大切です。
一つ目は、そこに「政治」も関係していると言うことです。
上述した若者のように、政治に期待できない現状があることも事実ですが、知事や議員を選ぶのは私たちです。
政治に関心を持って、投票に行く事は、重要な意思決定の場に私も参加したことになります。
たとえ、支持した候補者が当選しなくても、このプロセスが大切です。
重要な意思決定の場に参加するということは、共同体の中で自分の主体性も活かしていく行為で、自分の人生をより豊かなものにします。
アドラーの言う「自己受容」「他者信頼」「貢献感」に通じる内容で、幸福に繋がります。
二つ目は、今回の報道で、正しい言葉を使っている人と、間違った言葉を使っている人の違いにも気がつきました。
正しい言葉の世界で生きている人は、人生に意味を感じているし、しっかりとした軸を持ち、前に進んでいます。
間違った言葉、曖昧な言葉、自分でも理解していない言葉、人を惑わす言葉を使っている人は、苦しそうです。
人生に意味を見出していないかもしれません。
既に石丸叩きのような動きもあるようですが、国民のメディアリテラシーが上がることによって、国民をミスリードするマスメディアや、いわゆる「政治屋」は自然に淘汰されていくと信じています。
私たちは、正しい言葉の世界で生きるために、その能力や感性を磨いて、人生に意味を感じる生活にしたいものです。










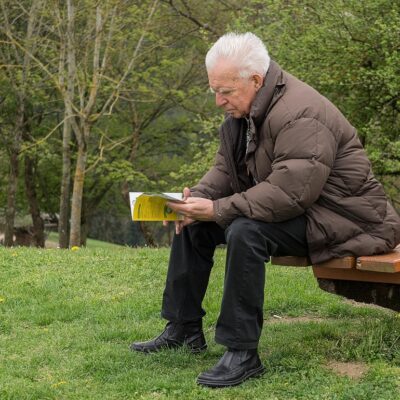




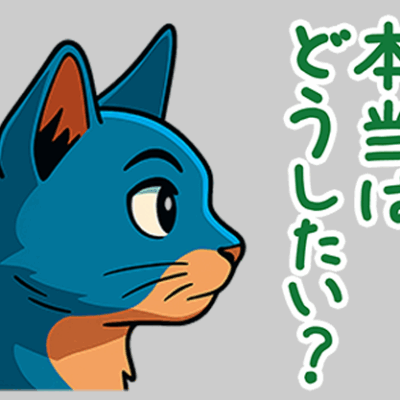







この記事へのコメントはありません。